
いろはのサービス紹介
「児童発達支援「放課後等デイサービス」
「保育所等訪問支援」
発達が気になるお子さんを、ご家庭や学校の中だけでサポートすることは容易なことではありません。
そのような子どもたちのためにあるのが「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などの発達支援施設です。
児童福祉法に基づいた施設であり、直接通うことで、必要なサポートを受けることができます。学童をイメージしていただくとわかりやすいかもしれません。
ただ、一般の学童と異なり、一人一人に「個別支援計画」という療育のプログラムが作られています。
そして利用にあたっては「受給者証」の申請が必要です。
(※療育とは…「障害のある子どもに対し、身体的・精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。 」厚生労働省HPより)
原則的に、小学生未満の未就学の子どもが通うことができるのが「児童発達支援」、小学生~高校生の就学児童が通うことができるのが「放課後等デイサービス」です。
「いろは」では子ども本人だけでなく、保護者の方のレスパイト(介護者の休息)とペアレントトレーニング(子育て支援)の役割も担っています。
お子さんの成長に合わせて、継続した支援をするために、「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」の両方を行っておりますので、気軽にご相談ください。
2024年~「保育所等訪問支援」のサービスを開始しました。
保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、認定こども 園、学校、放課後児童クラブなど集団生活を営む施設を訪問し、障害のない子どもとの集団生活 への適応のために専門的な支援を行うものです。
集団生活への適応のための専門的な支援とは、対象となる子どもを集団生活に合わせるのでは なく、子どもの特性等に集団生活の環境や活動の手順等を合わせていくことです。それには、保育所等での環境(他の子どもを含む集団の環境を含む)やそこで行われている教育や活動本人の 特性との両方を適切にアセスメントすることが求められ、その力が専門性ということになります。当事業所では、元学校教員・公認心理師・OT/PT等が訪問支援にあたります。

いろは
5領域のスキルトレーニング

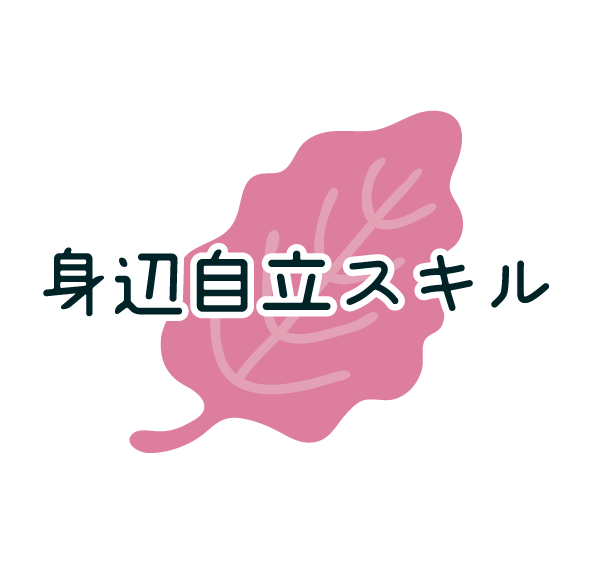




運動スキル(運動・感覚)
【ねらい】
①運動・動作・姿勢保持の向上及び補助的手段の活用
②保有感覚の総合的な活用
③感覚特性への対応
【具体的な活動】
・サーキットトレーング
・リトミック
・SIの遊具を用いた感覚統合療法
・手遊び、パズル、紐通しなどの机上課題
・粘土、スライム、製作活動
【具体的な支援内容・方法】
・走る、歩く、止まる、ジャンプする、座る、立つ、体をひねるなどの粗大運動を楽しく取り組めるようにリトミックなどの活動を取り入れる。
・作業療法、運動療法の専門指導を事業所内で行い、保有する能力の維持向上を図るとともに、日常の動作や遊びの中で活かせるようにその都度保護者と連携を図る。
・製作活動や遊びの中に多種多様な素材や題材を取り入れ、様々な感覚を楽しく経験できるよう支援を行う。
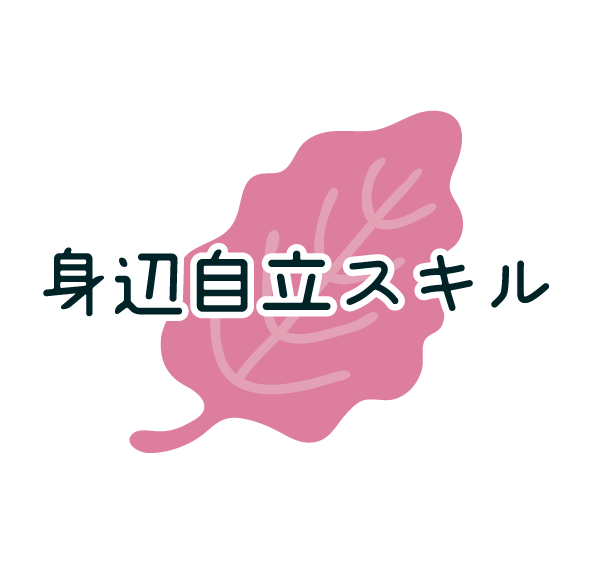
身辺自立スキル(健康・生活)
【ねらい】
①健康状態の維持・改善
②基本的生活リズムの獲得
③構造化等による生活環境の調整
【具体的な活動】
・食事のマナーを学ぶために事業所内でおやつの時間を設ける。
・手洗い、片付けなどの反復訓練
・カードや写真、ホワイトボードなどの活用
【具体的な支援内容・方法】
・定時排泄誘導、咀嚼の促し等
・定期的な利用による曜日の認識や定時の利用による生活リズムの安定を図る。同じ内容の活動を繰り返すことで、始まりと終わりの意識をすることに繋げる。
・それぞれのもっている力を保持増進し、一人でできることを増やしていけるよう、個々に応じた身体的、精神的、社会的訓練を日常生活動作の中で支援する。

学習スキル
(言語・コミュニケーション)
【ねらい】
児童発達支援
①言語の形成・受容・表出
②コミュニケーション手段の選択と活用(指さし・身振り・サイン・表情・模倣)
放課後等デイサービス
①読み書き能力の向上
②語彙の拡充
③学習困難に伴う困りの改善
【具体的な活動】
・絵本の読み聞かせや場面に応じた挨拶・自己紹介など
・絵カード、ジャスチャーの活用
・机上課題(めいろ、シール貼り、なぞり、模写など)
・語彙の拡充を図るためのゲーム活動、SST活動
・宿題のサポート等を通じた学習支援
【具体的な支援内容・方法】
・お子様一人一人の特性に合わせた具体的な体験や意味の理解ができるように目で見て理解できる情報を提示し、支援者が代弁して伝え、その場に応じた言葉を覚えられるように支援を行う。
・絵カードや写真カード・文字などのコミュニケーションツールを個々に応じて適切に選択して活用することで意思の伝達がスムーズにおこなえるよう支援をおこなう。
・KーabcⅡ検査の取得尺度を用いて、学習支援の方向性を決め、支援を行う。

コミュニケーションスキル
(人間関係・社会性)
【ねらい】
①他者との関わり(人間関係)の形成および自己理解と行動の調整
②愛着行動の形成
③模倣行動の形成・象徴遊び(見立て・つもり・ごっこ遊び)への支援
④社会性・対人関係の発達
⑤地域との交流
【具体的な活動】
・音楽療法(歌、楽器、リトミックなど)
・読み聞かせ(絵本・ペープサート・紙芝居など)
・小学生以上は小集団によるSST活動
・ボードゲームなどのルールをともった集団遊び
・地域の人を招いての行事活動
【具体的な支援内容・方法】
・個々にあわせた言葉や行動の支援を行い、支援者を介して自分の行動の特徴に気づくことで気持ちや感情の調整ができるようにする。また、信頼関係をもとに家族以外の周囲の人と安定した関係を形成できるよう支援する。
・触れる、聴く、歌う、話すなどのコミュニケーションを通して、お友達や支援者の動きを模倣することで社会性や対人関係の芽生えを支援する。(主として未就学児)
・個々の状況や状態に合わせ、個別活動と集団活動を組み合わせたりし、取り入れる。
・遠足や地域の方を招いた行事を行い、その交流を楽しめるように支援する。

余暇スキル(認知・行動)
【ねらい】
①認知発達と行動の習得(天気・気温・日付など)
②空間・時間・数量・大小・色・重さの概念の形成
③対象・外部環境の認知(物質の変化と感覚)と適切な行動の習得
④季節の変化への興味関心等の感性形成のための外出・行動
【具体的な活動】
・帰りの会、誕生日会、季節ごとのイベントなど
・ボールプール、トンネルくぐり、マッチングなど
・調理実習
・アート活動
・散歩、芋ほり、親子遠足などの外出活動
【具体的な支援内容・方針】
・K-abc 新版K式などの検査を用い、認知の特徴と傾向を分析する。
・お子様一人一人の特性に応じた、視覚・聴覚・触覚・固有感覚などを十分に活用し、必要な情報を収集しやすいよう色・音・形・素材・凸凹・写真や絵・文字・道具を用いて認知機能の発達を促す支援を行う。
・個別・小集団での活動支援の中で活動内容(環境)から情報を取得しやすいよう、イラストや写真を用いて手順を習得し、言葉や実際に支援者が演じてルールの説明を目で見て理解できる内容とし、実際に自らが行動につなげられるよう支援を行う。
・認知や行動の手掛かりとなる概念を、形成物の機能や属性、数量、大小、色、形の大きさ、重さ、色や形の違い・音に気付き、変化する様子を様々な活動の中で体験し、習得できるよう支援を行う。
・認知の偏りなど、個々の特性に配慮し、写真や絵カード、言葉がけなどを用いて自分の入ってくる情報を適切に処理ができるよう促し、自らも正しく行動できるように支援を行う。
・将来の就労にむけ、様々な余暇活動や就労体験を行う。
その他の支援内容



家族支援
移行支援
地域支援
・親子通所
・親子遠足
・懇談会の実施
・子育て支援に関する学習会の開催
・退所後も加入できる親の会を運営しています。
・お子様が保・幼・小・中に就学する際に、連携支援を行っています。
・サポートファイルかけはしの記入
・保育所等訪問支援により、専門的なかかわりを実施しています。
・夏祭り、マルシェ、作品展などの地域の方も参加できる行事を開催しています。
・専門学校の学生実習受け入れ。
・学生ボランティア等との交流機会を設けています。
「いろは」の時間割
送迎範囲:一宮 鶴尾 香川県立中部支援学校 各種保育園・幼稚園
※送迎につきましては、配車の数、感染症対策に伴う消毒作業等の都合上、お断りする場合もございます。申し訳ございません。なお、令和7年~は原則、自家用車をお持ちで無い方。運転免許所の無い方に限らせていただきます。
上記の学校以外につきましては要相談となります。



代表ごあいさつ
はじめまして。代表の岡です。
私はうまれも育ちも香川県、生粋の香川県民です。
「いろは」を立ち上げる前は県内で小学校の教員をしていました。
教員時代に結婚、出産し自分の子どもを育てていく中、我が子に育てにくさを感じることがありました。
子育てに悩み、でもどこに頼っていいか分からない毎日。「教員にもかかわらず、何故私は自分の子どもを、こんなにも育てられないのだろう」と情け無く思う辛い日々を当時は過ごしていました。
そんなとき支えになったのが、同じような悩みを持つ保護者と話す「場所」や、「療育」という支援の手段でした。
当時の私は、自分の子どもを「大人になったときに恥ずかしくないような立派な人間に育てなければ」という思いや「子育てがうまくできないことは恥ずかしいことだ」という思いばかりで、子どものできない部分ばかり目が行ってしまい、叱るばかりで、子どもの良さや強みに気がつく事ができませんでした。
今は、過去の私自身の経験が、同じような悩みを持つ方のお役に少しでも立てればいいなと思っています。
「いろは」という名前には、
『子どもたちが自分の持つ可能性を伸ばし、楽しみながら大人になってほしい。
そして彩り豊かな人生を歩んでほしい』そんな思いも込めてられています。
学校でもない、家庭でもない、でもここに来れば自分の居場所がある。
「いろは」はそんな場所でありたいと思っています。
代表プロフィール
岡 実樹
Oka Miki
元小学校教諭、男女2児を子育て中の母親。
教員退職後、株式会社オフィス岡を設立。整理収納業務と個別指導の学習塾経営を始める。
教員時代の経験を活かし、子どもの発達特性に合わせた学習支援を行うことを得意とする。
子ども自身へのアプローチのみならず、周囲の環境を整えることが大切と考えており「障がいの社会モデル」の理念を推奨している。
■保有資格
-
教員免許:小学校及び中学校(社会科)、高校(地理歴史)、特別支援学校
-
産業カウンセラー
-
整理収納アドバイザー
■所属学会
-
一般社団法人日本産業カウンセラー協会
-
一般社団法人日本 LD 学会
-
JAPAN MENSA会員

処遇改善に関する具体的な取組内容(職場環境要件)
弊社は、福祉・介護職員等処遇改善を取得しており、職員の労働環境処遇改善を実施しております。
職場環境要件として、下記の通り取り組んでおります。
入職促進に向けた取組
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みを構築しています。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・職員の資格取得のための費用一部負担。学習時間が確保できる勤務体系にしています。
両立支援・多様な働き方の推進
・有給休暇が取得しやすい環境を整備しています。
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制が充実しています。
腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策を実施しています。
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制を整備しています。
生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末の導入、労務の一部クラウド化により業務量を縮減しています。
やりがい・働きがいの醸成
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善に
取り組んでいます。




